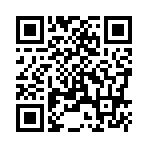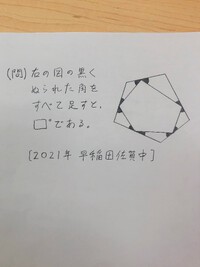平成27年度致遠館中入試(佐賀県立中適性検査)Ⅱ-「3」を考えてみよう!
2015年01月27日
明日(1/28)、いよいよ致遠館中、唐津東中、武雄青陵中、香楠中の佐賀県立中学校と佐賀大附属中の合格発表ですね!

ベストSの塾生を含め、受験生読者のみなさまの合格を願っています!!

さて、今日も致遠館中などの県立中高一貫校の今年の適性検査の入試問題を考えてみましょう!

適性検査の問題や評価の観点は、佐賀新聞HPをご参照ください!
平成27年度 県立中学校 適性検査(問題Ⅰ、問題Ⅱ、評価の観点)
(佐賀新聞HPリンク)
では、今日は、適性検査Ⅱの「3」を考えていきましょう!
「3」(1):間伐や枝打ちによって、森林の木々の成長具合が違い、森林組合の人が、
「間伐や枝打ちをするのは、どの木にも光や水、養分をよく行きわたらせるようにするためなのです。」
と話していることを参考にすると、実験では、
「光や水、養分がよく行きわたっている鉢」と「光や水、養分があまり行きわたっていない鉢」
の2種類の状態の鉢を作るようにします。
同じ面積の鉢に同じ量の日光や水、肥料が与えられるならば、植えられるインゲンマメが少ない方が、十分に日光や水、肥料を得ることができ、逆に、植えられるインゲンマメが多いと、1本あたりの得られる日光や水、肥料が少ないことになります。
(解答例)①種のまき方
②一方の鉢には、インゲンマメの種子を20個まき、もう一方の鉢には、インゲンマメの種子を40個まく。
(2つの鉢にまくインゲンマメの個数に差があれば、10個と50個でもよいと思います)
また、「育て方」としては、「間伐や枝打ち」同様に、「間引きを行って、光や水、養分をよく行きわたらせるようにする鉢」と「間引きをしない鉢」を用意する。
そして、この条件の場合、「間引きするか、しないか」の条件以外は同じにしなければならないので、最初に植える種子の個数は、同じにしなければならない。
(解答例)①育て方
2つの鉢に、インゲンマメの種子を30個ずつ植え、芽が出てから、2週間ほどして、ある程度成長したところで、一方の鉢は、弱っていたり、小さい苗を10本間引きするが、もう一方の鉢は、そのまま育てる。
(「2週間」という時期や「10本」という本数は、「1ヶ月間」や「15本」などでもよいと思います。)
「3」(2):間伐や枝打ちをしなかった森林では、木々の数が多いため、地表まで日光が届かなかったり、養分が十分に行きわたらず、背の低い植物などが育たないため、地面が見えている状態になっていると考えられます。
逆に、間伐や枝打ちをした森林では、木々の間が空き、地表まで日光が届き、養分が行きわたるため、背の低い植物なども育っていると考えられます。
そこで、背の低い植物がなく、地面が見えている森林に雨が降ると、表土が流されてしまい、土砂崩れなどの災害につながる恐れがありますが、木々に加え、背の低い植物が生えていると、直接、表土に雨が降り注ぐ割合が減るため、土砂流出が少なく済むと考えられます。
また、小さな草や植物でも、根が張ることによって、表土の強度が増し、土砂が流出しにくくなると言われています。
(解答例)森林の樹木だけでなく、背の低い植物が生えているおかげで、雨が直接土砂にあたらないし、根が張り巡らされているので、土砂が固められて、土砂が流れ出すのを防ぐため、土砂崩れを防ぐことにつながると思います。
森林の働きは、国語の説明文などでも出題されたり、社会の漁業に関連しても出題されることが多いので、よく調べておいてくださいね!
*参考HP
「もりの役割って何だろう ~森林のはたらき~」
(北海道水産林務部森林活用課HPリンク)
*応援のクリックをよろしくお願いします!!
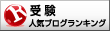
受験 ブログランキングへ

にほんブログ村


ベストSの塾生を含め、受験生読者のみなさまの合格を願っています!!


さて、今日も致遠館中などの県立中高一貫校の今年の適性検査の入試問題を考えてみましょう!


適性検査の問題や評価の観点は、佐賀新聞HPをご参照ください!

平成27年度 県立中学校 適性検査(問題Ⅰ、問題Ⅱ、評価の観点)
(佐賀新聞HPリンク)
では、今日は、適性検査Ⅱの「3」を考えていきましょう!

「3」(1):間伐や枝打ちによって、森林の木々の成長具合が違い、森林組合の人が、
「間伐や枝打ちをするのは、どの木にも光や水、養分をよく行きわたらせるようにするためなのです。」
と話していることを参考にすると、実験では、
「光や水、養分がよく行きわたっている鉢」と「光や水、養分があまり行きわたっていない鉢」
の2種類の状態の鉢を作るようにします。
同じ面積の鉢に同じ量の日光や水、肥料が与えられるならば、植えられるインゲンマメが少ない方が、十分に日光や水、肥料を得ることができ、逆に、植えられるインゲンマメが多いと、1本あたりの得られる日光や水、肥料が少ないことになります。
(解答例)①種のまき方
②一方の鉢には、インゲンマメの種子を20個まき、もう一方の鉢には、インゲンマメの種子を40個まく。
(2つの鉢にまくインゲンマメの個数に差があれば、10個と50個でもよいと思います)
また、「育て方」としては、「間伐や枝打ち」同様に、「間引きを行って、光や水、養分をよく行きわたらせるようにする鉢」と「間引きをしない鉢」を用意する。
そして、この条件の場合、「間引きするか、しないか」の条件以外は同じにしなければならないので、最初に植える種子の個数は、同じにしなければならない。
(解答例)①育て方
2つの鉢に、インゲンマメの種子を30個ずつ植え、芽が出てから、2週間ほどして、ある程度成長したところで、一方の鉢は、弱っていたり、小さい苗を10本間引きするが、もう一方の鉢は、そのまま育てる。
(「2週間」という時期や「10本」という本数は、「1ヶ月間」や「15本」などでもよいと思います。)
「3」(2):間伐や枝打ちをしなかった森林では、木々の数が多いため、地表まで日光が届かなかったり、養分が十分に行きわたらず、背の低い植物などが育たないため、地面が見えている状態になっていると考えられます。
逆に、間伐や枝打ちをした森林では、木々の間が空き、地表まで日光が届き、養分が行きわたるため、背の低い植物なども育っていると考えられます。
そこで、背の低い植物がなく、地面が見えている森林に雨が降ると、表土が流されてしまい、土砂崩れなどの災害につながる恐れがありますが、木々に加え、背の低い植物が生えていると、直接、表土に雨が降り注ぐ割合が減るため、土砂流出が少なく済むと考えられます。
また、小さな草や植物でも、根が張ることによって、表土の強度が増し、土砂が流出しにくくなると言われています。
(解答例)森林の樹木だけでなく、背の低い植物が生えているおかげで、雨が直接土砂にあたらないし、根が張り巡らされているので、土砂が固められて、土砂が流れ出すのを防ぐため、土砂崩れを防ぐことにつながると思います。
森林の働きは、国語の説明文などでも出題されたり、社会の漁業に関連しても出題されることが多いので、よく調べておいてくださいね!

*参考HP
「もりの役割って何だろう ~森林のはたらき~」
(北海道水産林務部森林活用課HPリンク)
*応援のクリックをよろしくお願いします!!

受験 ブログランキングへ
にほんブログ村